「キャパシター・ディスチャージド・イグニッション・システム」の略です。
構造的には下のようになっています。
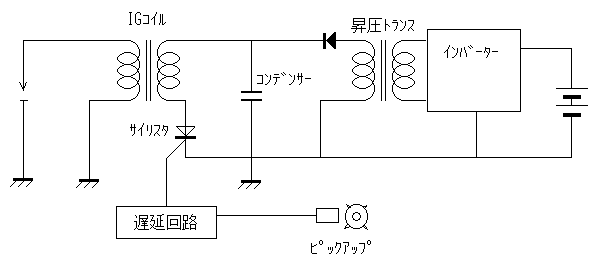
バッテリー電圧は、内部のインバーターにより20〜40V程度まで昇圧され、それがコンデンサーに蓄えられます。
点火時期がくると、コンデンサーからコイルに向けて一気に電流を流し込みます。
すると、さらに高い高圧電流がプラグに流れ込む構造です。
通常、エンジンでは常に回転数が変化しています。
点火時期は、センサーが点火時期を捕らえてから、コンピューターが算出した時間分まってから点火させます。
そのため、センサーの点火時期は、実際の点火時期より早い位置(進んだ位置)で信号を発生させています。
そのため、急激な回転上昇があった場合、点火時期は遅れ気味に、回転低下がしれば進みに気味にならざるを得ません。
それを防ぐため、クランクの角度を読み取り、何度進んだかで点火時期を制御する方法にすることで、急激な回転変化でも確実な点火時期にする事が可能となります。
良いことづくめのC.D.Iですが、欠点もあります。
一つは放電時間が短い事です。コンデンサーに蓄えられた電流量しかトランスに送れないので、どうしても放電時間が短くなってしまいます。
その為、超高回転では着火ミスが出易くなります。いくら電圧が高くても電流値が少ないと、放電温度が上がらないためです。
また、最近ではIGコイルの性能も良くなり、ノーマルの点火方式でも十分な点火エネルギーを供給できるようになりました。
そのため、バイク用のエンジンぐらいにしかC.D.Iが採用されなくなってきました。
CDIの高速着火能力を利用し、低回転では3回、中回転では2回というふうに数回に分けて放電させ、着火温度を上げる方式を採用するメーカーも出てきました。
通称、MDIと呼ばれるものです。
コンデンサーを二次側に取り付けた方法もあり、この場合は簡易に後付けが可能なため今までにさまざまな方式がありました。
