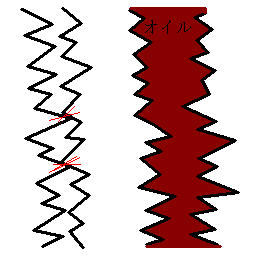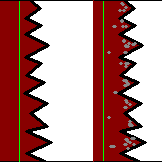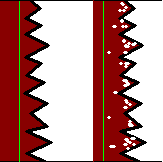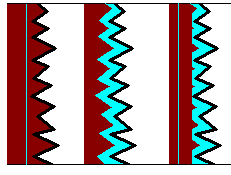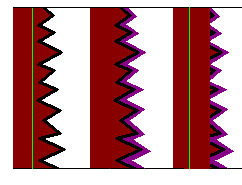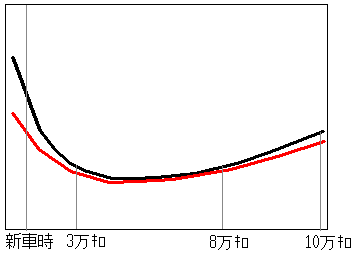オイル添加剤
- オイルを買うとき、同じように添加剤も沢山並べられています。
-
タイトルや効能を読む限りでは、「ぜひ入れてみたい」と気持ちをそそるものばかり。
ところが、入れてみると思ったより効かなかった。効果がないと言われる人が多くいます。
効かないものを売れば、立派な詐欺です。
2008年初頭、そういった製品に排除勧告が出された事例がありました。
訴える前に、まず、あなたのエンジンがその添加剤を要求していない!という可能性もあります。
その辺りのことを掘り下げてみようと思います。
- 潤滑の仕組み
-
難しい事は置いておき、簡単にさっと説明してしまいます。(トライボロジーとかの小難しい話しは嫌でしょ)
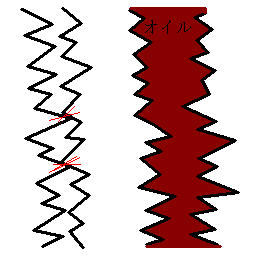
キラキラと鏡のように光る金属面。
しかし、それを顕微鏡で見れば、 無数のキズがみえます。
この傷同士が噛み合うことで摩擦が生まれ、動きが硬くなります。
そこにオイルが入れば両者の間に油の膜が生まれ、その膜に金属が浮かぶことで両者に隙間が生まれます。
その引間が無数の傷が噛み合うのを防ぎ、抵抗を減らしています。
これが潤滑の大雑把て理屈です。
ちなみに、傷も無いほどに磨き上げられ、平面化した金属同士では、触れさせると空気の膜で氷のように滑ります。
その後、空気が抜けると両者が吸い付き、一体となり離れなくなり、ずらす事さえ出来なくなります。これを「真空接着」といいます。
- 傷にも色々
-

一般に傷といってもさまざまな深さ、大きさの傷があります。
LAP加工された金属表面の傷の大きさは深さ、幅ともに1μ程度です。(図左側)
しかし、金属同士がそんな状態同士では、周辺部のオイルが先に逃げてしまい、接触面中央部ではオイル切れが起こしてしまいます。
それを防ぐために、片方の金属面に結晶化させた金属を蒸着させてることで細かなデコボコを作り、オイルの供給源にしてあります。
この傷の深さは深く、5〜10μ程度です。
また、メタル部にはオイル経路があり、そこから絶えずオイルが供給されていますが、エンジンのシリンダーには飛び散った油分しか供給されません。
そこで、ホーニングという加工を施して、オイルの供給を可能としています。
この傷は深さは深さも幅も10μ以上あります。
- 代表的な添加剤成分
-
- モリブデン系
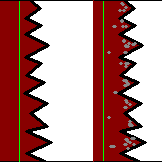
モリブデンと呼ばれる金属を添加剤として使用しています。
この金属は単体では固体で、またモロモロと大きな塊となるため、通常は有機物や硫黄などと化合させお互いに引っ付かないようにして、オイル内部に漂わせた状態で添加させています。
エンジンオイルに最初から添加するタイプにこれが使用されています。
モリブデン自体は金属なので、金属と相性が良く、表面にへばりつきます。
へばり付いたモリブデンは、微小凹凸の凸部についたものは相手側の金属がすぐに削り落とされ、凹部についたものはその場でとどまります。
やがて傷の中に溜まったモリブデンの為に、オイルが押し上げられ、油膜が厚くなり、擦動抵抗が低くなります。
- テフロン
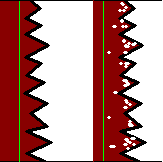
店頭に並ぶ商品で後から添加するタイプではこのものを使用している場合が多いようです。
一種の樹脂ですか耐熱性が高く、120℃ぐらいまで絶えれます。
モリブデンの時と同じ原理です。金属表面の傷内部にとどまり、油膜を押し上げます。
モリブデンより柔らかい樹脂なので、相手側の金属を傷つけることもありません。
ただ、金属表面にはモリブデンよりもくっつきにくいので、各社さまざまな工夫をして、金属表面にとどまるようにしています。
- チタン等の液体金属
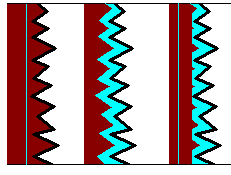
金属を薬剤で溶解させたものをオイルに添加しています。
エンジン内部に入ると、一様に金属表面に付着し、金属表面に膜を作ります。
ただし、膜といっても言うほども強固ではなく、金属同士の擦動ですぐに磨耗していまいます。
しかし溝奥に析出した金属は、触れられることが無いため、その場にとどまります。
こうやって、傷を埋めてしまい、油膜を押し上げます。
- リン・塩素等の極圧剤
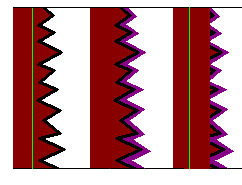
通常、ギアオイル等に添加される極圧剤をエンジンオイルに添加します。
極圧剤は金属同士が高温高圧下に置かれると、鉄の原子と結合し、化合物になります。
この化合物は、鉄よりも柔らかい為、すり合わされて表面が原子1枚の層となり削り取られます。
ハイポイドギア等はこのような理屈で潤滑されています。
エンジン内でも同じようなことがおきています。
金属表面に結合し、やわらかい金属に変化します。
それが摩擦で削られて、やがて平坦な金属面がとなります。
削られるといっても、大きく削られるわけではなく、ほんの数ミクロン程度の磨耗です。
これは暫くエンジンをつかい、当たりが付いてきた頃の状態です。
つまり、短時間で当たりを付けるのと同じ原理です。
その他
波動や放射線を用いるタイプです。
科学的な理屈ははっきりわかりませんが、全てのものが効果が全くないわけではありません。(効果は感じられない人は沢山いますが)
科学は万能では無く、我々の周りで起きる全ての事柄のほんの一握りが科学で証明されている事柄です。
その証明の根本も実は不明であることの方が大きく、調べれば調べるほど「科学」というのはあやふやでいい加減なものだと感じます。
そのうち、解明される日が来るでしょうね。
出来れば私が生きている内に解明していただきたいものです。
添加剤の効果
添加剤はそのもの自体が潤滑を助けるわけではなく、たいていは油膜を厚くする働きがあります。
ですからテフロンやモリブデンといったものはそのもの自体でも潤滑作用がありますが、それを利用しているわけではありません。
「鉄より柔らかい」という性質のみを利用しているのです。
当然、柔らかい金属でる錫や鉛でも良いのですが、こういったものでは分散(オイル内部に漂う状態)がしにくく、エンジンを構成する金属と相性が悪いため使用できません。
その昔は、石英やダイヤモンドといった、一種の研磨剤としか考えられないようなものを使用した添加剤もあったほどです。
添加剤が効く、効かないの別れ道
添加剤を通常、どのようなものだとお考えですか?。
一種のカンフル剤のように、くたびれてしまったエンジンを新品ちかくにまで蘇らせるものだと勘違いしていませんか?。
このグラフを見てください。
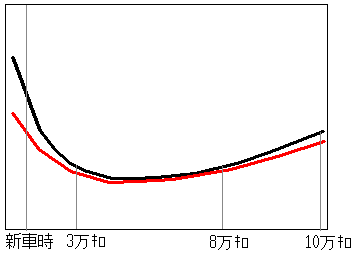
縦軸には摩擦損失、横軸が走行距離です。
新車からエンジンを動かすと、どんどんとフリクション・ロスが低下してゆきます。
これは金属同士が摺り合わされて、磨耗が少なくなってきているからです。
そしてある程度使い込むと、今度は磨耗や、擦動方向にキズが着き、それが原因で摩擦が増えてきます。
添加剤を加えた時の摩擦の変化を赤線で重ねています。
通常、添加剤を使ってみたく頃である4〜6万キロ辺りではほとんど差は見られません。(ディーゼル車の場合は、大抵10万キロを超えたぐらいから)
つまり、みなさんが添加剤を使っているころと合致してしまっています。
これでは折角の添加剤も意味がありません。
そう。これが添加剤は効果がないと思われる一番の原因だと思います。
元々、エンジンに当たりが付き、調子よくなったころに添加剤を使っても、思うほども効果がでるはずがありません。
使うなら、新車で購入してすぐ!。またはO/Hをした直後からがもっとも効果がでる時期でしょう。
7万キロ以上走ったのであれば、o/h等のメンテをした方がずっと効果があります。
(もし、興味があるならば添加剤のレビュー等をごらんになってください。否定派は大抵は使い込んだ車、肯定派は新車などを比較対象としていますから。)
結論
添加剤は正しく使えば、うたい文句までも性能向上は無いものの、効果がでます。
しかし、使い方を誤れば効果はでません。
よく間違った使い方も聞きます。
- 添加量を増やせば効果も大きい
全くの逆です。パッケージ等で書かれている添加量は「最大添加量」だと認識してください。
私が試したいくつかの添加剤では、効果が大きく感じたのは、指示された添加量より少ない量でした。
まずは指定量の半分ぐらい入れてみる。
そんな所からはじめてみると良いでしょう。
- 添加剤はチャンポンしない
基本中の基本です。使用する添加剤は必ず一種類だけです。
また、エンジンオイル添加剤と燃料添加剤のように入れる場所が異なる添加剤も同様に、同時に試さないでください。
必ずどちらか一方で試して見て、効果がでたなら、一度辞め、もう一方の添加剤を試してみるべきです。
その後、同時に使用します。
そうしないと、どちらが効果があったのか解らないからです。
- 用法はとりあえず守る
本当に効果がある添加剤は、他の部位にも使用できる場合があります。
まずは、指示された部分で効果を確かめ、それが効くならば他の場所でも試してみるべきです。
某添加剤は、フロントフォークやリヤサスのロッドに塗っても効果がでます。
乗り心地や追従性が良くなりますので、一度試してみるのも一計です。