通常のダイオードも実は発光していますが、可視光線ではないので、見えないだけです。
逆に、ダイオードに光を当てると、電気が起きます。効率が悪いだけです。効率を良くしたのが、フォトトランジスタだったり、太陽電池だったりします。
詳しいことは、いろんなサイト回ってみてください。
- 消費電力が少なく、発光効率が良い。電球の1/10ほどの電力で同等の明るさを得ることができます。
- 単色光の光がでる。波長が揃っているため、無駄な光がでません。反面、カラーフィルターなどを被せると、その光がでていなと非常に暗くなります。
- 電球と違い、電気の流れる方向が重要で、流れが逆になると発光しませんし、電気も流れません。
(無理に流すと壊れます) - 光の指向性が高く、光が集中します。
技術の進歩ですね。
さて、こんなLEDでは定格を超えると一瞬で壊れるというもろい面を持っています。
気をつけなければならないのが、回路です。
特に、定格ギリギリの限界近くで使用して、明るさを得ている場合、条件が揃うと簡単に破壊されてしまいます。
CRD(定電流ダイオード)などの電流制限回路でも抑えきれない場面もあります。
問題になるのはスイッチ。
下のような回路があります。便宜上、電池2本ですが、12vかかってるのもとして考えてください。
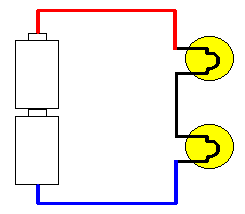
直列に並んだ同じ定格の電球が二つあり、現在点灯しています。
当然、各電球には電源電圧の半分の6vがそれぞれの電球にかかって、点灯しています
いま、片方の電球を抜くと、両方の電球が消えてしまいます。
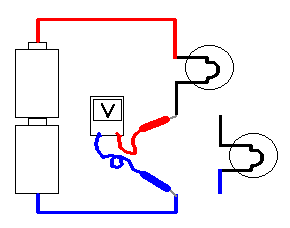 このとき、テスターの電圧を測定すると、一体何vでしょうか?。
このとき、テスターの電圧を測定すると、一体何vでしょうか?。この問題、以外と答えられない人が多いのには驚かされます。
答えは12vです。
テスターで測定すると12vの電圧がしっかりかかっています。一度測定してみるとよく分かると思います。
同じことがLEDの回路でも言えます。
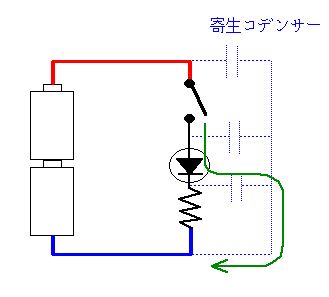 電流が流れていない状態では、全部の部分に12vの電圧がかかっているのです。
電流が流れていない状態では、全部の部分に12vの電圧がかかっているのです。本来はこれを見越した定格で計算されていますが、定格ギリギリの場合、長時間点灯し、LEDが発熱。
その熱量のまま点灯させたとき、回路中の静電容量分の電流がほんの一瞬ですが、大電流がLEDに流れることになります。
これが半永久と言われるはずのLEDが破壊される仕組みです。
他にも、ノイズやLEDランプの場合、複数列使用されることが多いのですが、その電流の偏りなどによっても破壊されます。
対策としては、12vの電圧が加わらないように、スイッチに点灯しない程度の高抵抗の抵抗を噛ませることで、対策は可能です。
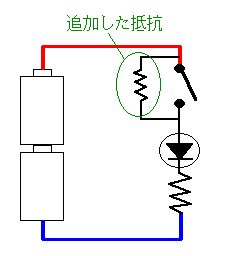 他にも、半導体スイッチを使用する手もあります。
他にも、半導体スイッチを使用する手もあります。この方式ハロゲンランプの長寿命化にも応用できます。
通常、ランプは点灯直後に大電流が流れます。突入電流と呼ばれるものです。
大抵はこの衝撃で、フィラメント自体が変形し、それが引き金となり破壊され、寿命を迎えます。
所が、弱い電流を流すことでフィラメントを保護、点灯時の突入電流を減らすことができます。
LEDと違い、ハロゲンで保温電流を流す場合は、比べて多くの電流を流さないといけないため、スイッチにつけるのは不経済です。
車などでは、スモールランプから抵抗を介して保温電流を取り出した方が良いでしょう。
常時点灯しているバイクの場合、IGスイッチと連動していることが多いので、コンデンサーなどを並列に接続してしまうのも手です。
確かにCRDの方が定格ギリギリまで使えて明るさが得られます。
明るさが欲しければもう一列、LEDを増やせば済むだけではないでしょうか?
電球に比べてサイズの小さなLEDですからなんとかなるものです。
また、回路設計においては、列毎にそれぞれ電流制限を行ってください。
でないと、一つのLEDが故障した場合、連鎖的に故障する可能性があります。
LEDに交換する部分は大抵はテールランプやウインカーといったものだと思います。
これらは重要保安部品です。
場合によっては「故障しました」では済まされない事態もあるでしょう。
その点を考えて、LED化を進めてください。点灯すれば良いというわけではないので。
