単に、電球を置いただけでは、四方八方に光が散乱してしまい目的の箇所に光があたらず、効率の悪い物になってしまいます。
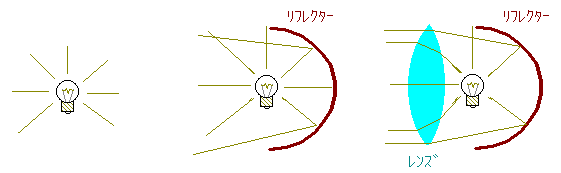
そこて、側方や後方の不要な光を前に照射するための、反射板(リフレクター)を装着し、前方により多くの光を送ります。
ただ、それだけでは、目的の部分以外も照らしてしまうため、それを防ぐためにレンズを装着し、光を揃えて目的の部分を明るく照らすようにしています。
しかし大きなレンズでは重量が重くなりすぎてしまいます。
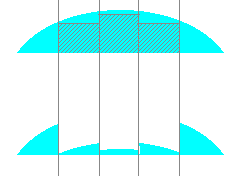
そこで、レンズ内部のレンズとして作用していないガラスの直方体の部分をカットして軽く作ったフレネル式レンズが使われました。
現在でも、灯台などにはこのレンズが使用されています。
ただ、フレネル式レンズを使用するとコストが高くなるため、各レンズを配光パターンに似合った小さなレンズを作こんだのが通常のライトです。
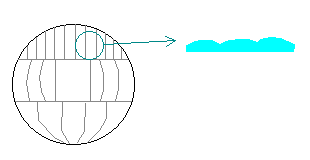
小さなレンズの集合体にすることで、好みの方向に光をむけることができ、また、厚みも薄くできるため軽く、安く作れるようになりました。
そうなると、レンズをそのまま使用しても、重量増加を抑えれるようになりました。
また全面投影面積を小さくすることで、空気抵抗を下げることや異形ヘッドライトの採用などでレンズ直径を小さくせざるおえない状況になってきました。
そこで採用されたのが、プロジェクターヘッドランプです。
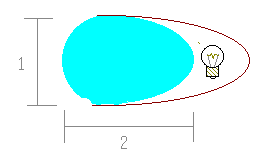
見た目は小さいレンズ径ですが、奥行きが長く、おおよそ直径の倍はあり、リフレクターを含めると3倍ほどの奥行きになります。
光がほぼまっすぐにでて、スポットライトの様に照射します。
光の拡散が少ないため、主にハイピーム用として使用されていました。
軽量化の為、フレネル式レンズを採用した車もありましたが、(たしかBMWだったと思う)製造コストがすごく高く、また、レンズ内での光の進路に角度がついているため余分な方向に光が反射して効率が悪かったようです。
そこで、レンズを複数個使用することで、奥行きを短くする方法が考えられました。
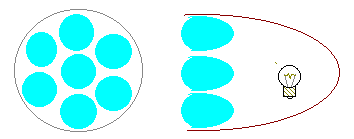
こうすることで、レンズ一つ当たりの奥行きが短くなるため、全体に短く、軽くできるようになりました。
どこかで見かけたことがあるランプだと思います。そう、あの車のランプです。
そのため、レンズ等を使用すると、波長差などにより光が分離し、また、レンズ同士の継ぎ目では光が拡散して効率がどうしても悪くなりがちです。
ガラスや樹脂の中を通るときの喪失もバカになりません。
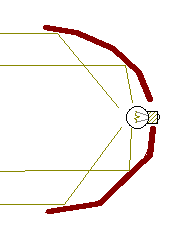
そこで、リフレクター自体を高度に設計し、小さな鏡の集合体と見なし、それぞれの鏡が目的の場所を照らすようにすることで、そのロスを極限までに抑えたのがマルチリフレクター式のライトです。
通常、ランプが丸形がもっとも効率が良く、異形ではどうしても効率が落ちがちでした。
この方法を使うことで、異形でも効率よりく配光でき、しかもレンズ等を使用しないので損失が少ないランブが出来るようになりました。
ただ、電球自体のフィラメントの位置と、口金の精度が要求されるため、安い電球では光軸がずれたり、最も効率のよい場所から、フィラメントの位置がずれたりします。
こういった部分でも価格差による明るさの差がでてきます。
今でもたまにそうしている人を見かけます。
しかし、今の車は樹脂レンズ、または樹脂カバーなので、ガムテープを張るとそこが高温になり、樹脂が変色したり変形したりもします。
そういった事で、今では使われなくなった手法です。最近は量販店があちらこちらにあり、すぐに電球が入手できる環境になるからでしょうね。
その試か、よく間違えてガムテープを貼っている人がいます。
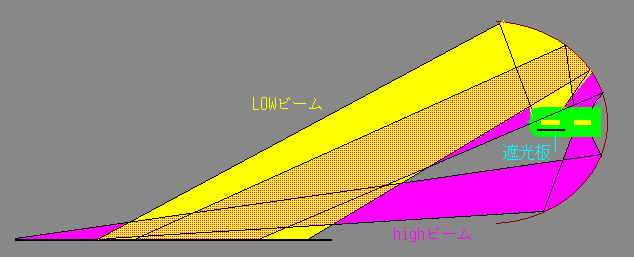
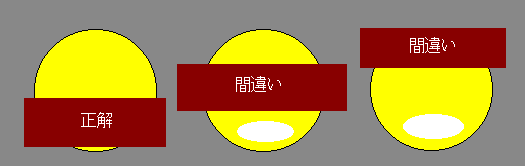
ランブの下にある白い部分が輝点です。これが見えると眩しく感じます。
ハイビームはランプの下側を隠さないと意味がないのです。
上側は主に道路の手前を、ランプの下側は遠くを照らしているからです。
また、真ん中も意味がありません。なぜなら、バルブの先端には大抵は遮光カバーがついているからです。
注記、ないランプもあります。
