その光の色を「色温度」と呼ばれる温度で表したのが色温度です。
単位は「k:ケルビン」、絶対温度と呼ばれるもので、これ以上下げることができない物理的限界の温度を0kとして目盛りをつけたものです。
0kは、-273.16℃です。目盛りの間隔は℃と一緒になっています。
そのときの金属温度を絶対温度で表したのが、「色温度」です。
そのため、明るさとは無関係です。
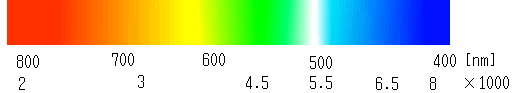 上の数字が波長の長さ(単位はnm:ナノメートル)です。
上の数字が波長の長さ(単位はnm:ナノメートル)です。下の数字が色温度(単位はk:ゲルビン)となっています。
あくまでも、これはその色が、金属の発光色と一緒なだけて、フィラメント自体がその温度になっている訳ではありません。
例えば、澄みきった青空が7000℃の高温であるわけでもありませんし、青信号の電球が、5000℃の温度を発しているわけでもありません。
色の基準です。
確かに、フィラメント自体がその色温度を発しているとすれば、それはすごく明るい事を意味します。
それだけ高温なのですから、発光量も素晴らしく、消費電力も半端でなくバカでかくなります。
そして寿命も短く、点灯した瞬間で終わってしまうでしょう。
でも、そんなものは商品にはなりません。
ですから、バルブ表面にコーティングを施して、青く見えるようにしているのです。
当然、余分な赤い光をカットしますから、その分は暗くなります。
青いほど、暗いのはそのためです。
ところが、青く光るのに、金色や橙色をしたコーティングの電球があります。
青いコーティングをしていると、フィラメントから出た光の内、青い光のみ透過して、残りの光は色素に吸収される事で青い光が出ます。
金色や柿色のコーティングは、青い光以外を反射するコーティングです。
ですから、電球をみたとき、青い光は透過し、残りの光が反射して見えるため、白い色(自然光)より青を抜いた光が見えるのです。
こちらの方式だと、熱線や他の色の光は内部で反射し、フィラメントをより高温にすることが可能で、発光効率があがります。
