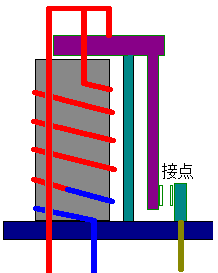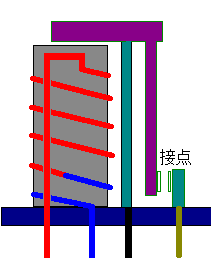これがノーマル・ホーン。1個のみ。
場所は、フロントバンパー裏の、バンパー骨材のさらに裏。
どうやっても手も工具も入りません。
ホーンのとりつけ
オーナー曰く、こういうコンパクトカーって舐められることが多いそうです。
そういうわけで、取り付けの依頼をされました。
これといって、難しい施工ではありませんが、コンパクトカーの場合、部品点数を減らすために一体化した部分が多いため、そこに辿り着くまで手間がかかるものでした。
取り付けには、電気の配線を要します。ここの注意を読んでから行ってください。

これがノーマル・ホーン。1個のみ。
場所は、フロントバンパー裏の、バンパー骨材のさらに裏。
どうやっても手も工具も入りません。

結局、ここまで分解して取り付ける羽目に。
すごく分解しているように見えますけど、バンパーとナンバープレートを外しただけです。
バンパーは結構な本数のビスと、ワンタッチ・ピンで固定されています。また、アンダーカバーやタイヤハウス内のカバーとも固定されているので、固定箇所は結構多いです。


ホーンをステーに取り付けて、それを元のホーンと交換して終わり。
配線は元の線に取り付けて、あとは元に戻せば完了です。
あれ?リレー着けなくていいの?
今回は、必要ありませんでした。なぜならば、ノーマルホーンに来ている線が一本だけでしたし、ホーン自体消費電力の小さな「ノーマル交換型」だったためです。
ホーン周りの配線方法はメーカーによって色々あり、必要な車種とそうでない車種があります。
また、エアホーンや大音量のものでは消費電力が大きく、その場合はリレーを増設しなければなりません。
バイクは自動車のホーンを流用する場合、基本的にリレーは必要です。(なくてもいけますてど)
タイプ別、配線図
一般的なホーン周りの配線図です。運転席エアバック非装着車に多い回路です。
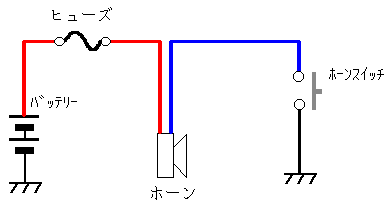
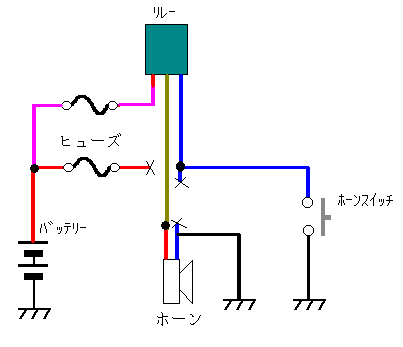
ホーンの所に「常時電源」と「信号線」の2本来ているのが特徴です。
このタイプはリレーを装着しないと、大きな音がならない場合が多いようです。
リレーは3端子のものを使用します。
エアバック装着車に多いタイプの配線図です。
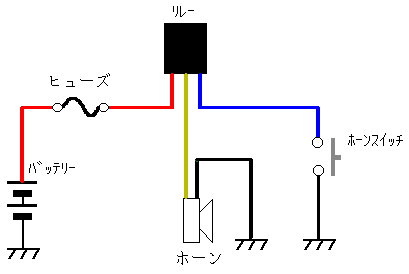
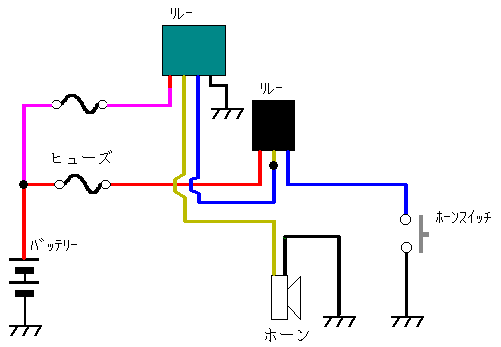
既にホーンリレー(純正、黒色)が装着されており、別途リレーを装着する必要はありません。
ホーンの所に信号線が一本だけ来ているのが特徴です。
ホーン本体もそれに合わせて設計されているため、端子が一本しかありまん。
ホーンの取り付ける場合、ホーンのマイナス端子はボディーアースをとります。
リレーがついているので、通常は必要ありませんが、大電力を要するホーンを取り付ける場合、純正では少し心細いのでリレーを取り付けても良いでしょう。
その場合、使用するリレーには4端子リレーを選びます。
ちなみに、コルトはこのタイプでした。
あまりありませんが、こういうタイプもあります。
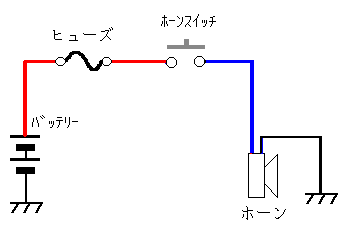
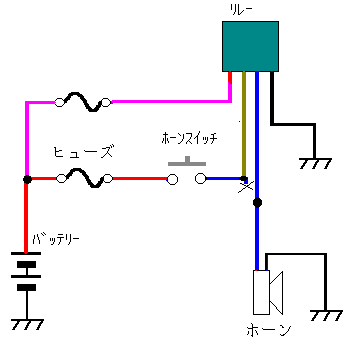
ホーンを取り付けてみて、音が小さいようでしたらこのタイプでしょう。
ホーンを組み込む前に、一度仮配線を施し、上手くなるか様子をみた方が良いと思います。
配線は信号線一本のみです。
リレーには必ず4端子リレーを使用します。
まれにこういうタイプもあります。
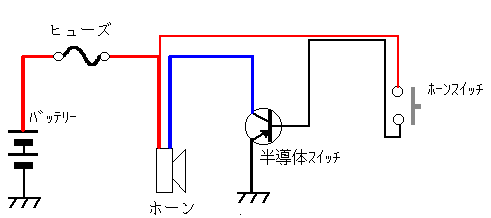
アエバック装着で、ホーン線が2本ある場合、こういうタイプが潜んでいます。
念のため、リレーを装着したほうが良いでしょう。
こういったタイプでは、ハンドルのエアバックの電源と共用している場合が多いので、配線ミスや衝突時に断線を起こしたりすると、エアバックが不必要に展開したりして危険です。
リレーの装着方法は、通常のタイプと同様です。
リレーの中身