バイクで走ってるとき、信号で止められてしまう事がよくあります。
できれば、信号で止まらないで通勤できれば快適ですよね。
(何カ月か、通勤していると次第にタイミングとか覚えてきて、それなりに止まらないように走れる様になりますけど。)
通勤中、信号待ちで暇だなと思ったり、ゲーム感覚でやってみるのもおもしろいかもしれませんよ。
- メモ帳台を作る
- 電波時計の購入。
- 信号間の距離と特徴を控える。
- 攻略開始
- 集計開始
- 独立型
- 感応型
- 連動型
- 曜日ごとの集計が終わり、信号の周期が判ると、区間速度を求めます。
走行中にでもメモ書きできるよう、こんなメモ台をつくりました。
 雨に打たれ、ペンは途中で落とし・・・改良の余地ありすぎ。(笑)
雨に打たれ、ペンは途中で落とし・・・改良の余地ありすぎ。(笑)攻略の為には正確な時刻は不可欠です。
XRに搭載される時計はなぜか一週間に1秒の速さで遅れてゆきます・・・・。
脇道から幹線道路への合流には○印。
幹線道路と幹線道路の交わる交差点には●印というように、印をつけておきましょう。
交差点名も忘れずに。(A,B,Cの記号でも可)
止まった交差点の名前と、青になった時刻を記入。
一定量の情報が集まるまで、収拾します。
その間は普通に通勤します。
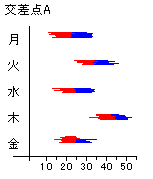 ある、交差点のパターン図です。
ある、交差点のパターン図です。
通常、信号は一定時間で切り替わってますが、取り付けられる場所によって下の様な種類があるようです。
おもに一般道に配置されています。時刻によって信号パターンを変化するのもあります。
一般道から幹線道路、狭い、通行量の少ない道から広い交通量の多い道に取り付けられています。
車を感知するレーダーが頭上にあります。
バイクの場合、左端に止まる反応してくれない事が多いです。できるだけ、レーダーの下に。
ただし、いくつか信号をクリアすると、必ず止まる様になっています。
上の図では、「感応型」か「連動型」のいずれかだと思われます。
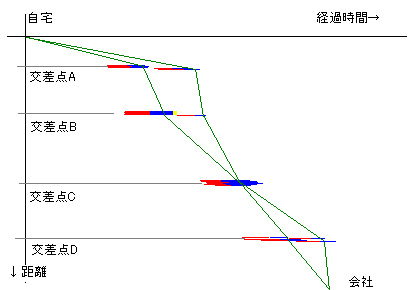
青の時間を結んだ直線、緑色がその区間の平均速度となまりす。
角度が緩いのはゆっくり、急な部分は早く走ることを意味しています。
例のグラフでは交差点A-B間を早く走り抜けないと信号に引っかかる事を示しています。
また、自宅の出る時刻も、もう少し遅くても会社につく時間が変わらない事も読み取れます。
区間速度が別れは、後は最初にひっかかる交差点Aの信号時間を基準に走れば良いので
いちいち時計を合わせる必要もありませんし、理屈上では最初にかかる交差点Aのみに引っかかるだけです。
実際は渋滞等で区間速度がだせず、間に合わないという事も多々あります。
でも、これを知っていると知らないとではかなりの差が出ると思います。
また信号のつながりが悪い場合、ルートを変更するのも一案です。
実際、大回りでも信号の関係で早くつく場合も多いですので、色々研究してみてはどうでしょうか?。
私の場合、片道16kmの通勤で、信号にかかる回数は平均3回です。
遅刻したりするとタイミンクグが変わってしまい、信号にかかる回数が増えてしまいます。(笑)
あと、信号のパターンを変えられると、また一からやり直し・・・・
